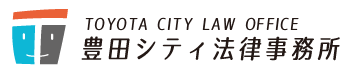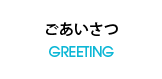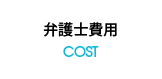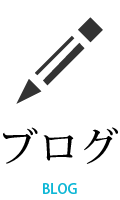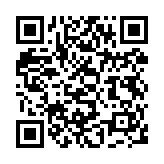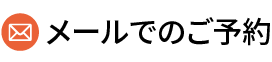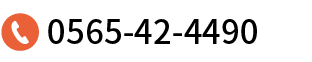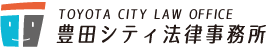未払残業代の消滅時効
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、前回は未払残業代について取り上げましたが、改正民法との関係も触れておいた方がいいと思い、今回再び取り上げます。
賃金にかかる請求権は現在労働基準法で「時効は2年」とされています。この定めにより、退職社員が未払い残業代などの請求をする際には、時効にかからない直近2年分の請求をすることが通例ですが、この時効にかかる規定が「5年」に延長されることが検討されています。中小企業経営には大きな影響を及ぼすことが予想されます。
この話題の前提として、消滅時効にかかる民法改正を知る必要があります。これまで民法では「賃金などの債権を含む頻繁で小額な債権の短期消滅時効は1年」「一般債権については権利行使できるときから10年で時効」とされていましたが、平成32(令和2)年4月1日から、時代に合わせて「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」「権利を行使することができるときから10年間」で時効消滅するよう改正されました。
問題は、労働基準法との関係です。
労働基準法は民法の特別法であり、今までは「民法では1年の時効だが特別法により2年(退職金については5年)」という時効が定められて運用されてきました。
しかし、民法で時効が5年に改正されることを受けて、「賃金債権を特別に短くする理由がない」ということで労基法における賃金債権消滅時効も5年に合わせるよう改正が検討されています。
時効が5年になったら賃金債権の消滅時効が5年に改正されると、次のような影響があると考えられます。
【1.未払い残業代請求事件が増える】
過去5年分の未払い残業代請求ができるとなると、今までよりも高額な報酬が見込めることから未払い残業代請求を専門とする弁護士が増えて、今よりもさらに未払い残業代請求訴訟が増えることが予想されます。未払い残業代請求を促す広告も世の中に増えるでしょう。
【2.名ばかり管理職問題が再燃する】
名ばかり管理職として働いている労働者からの未払い残業代請求の動きが再燃する可能性があります。請求できる金額が増えることで、「管理職だから残業代を支払わない」という安易な労務管理の問題点を突く訴えが相次ぐかもしれません。
ここは手当等をやめて基礎収入を低めにしておいて、その代わり残業代をきっちり払う、というやり方などが対応として考えられます。
うちの事務所でも経験がありますが、長時間労働をしている管理職は残業単価も高いため、未払い残業代請求が高額化する点で危険度が高くなります。管理監督者として扱うのであれば裁判になっても絶対勝てるような待遇や責任を与える必要があり、やるなら万全の体制でやるべきでしょう(中途半端が一番ダメです)。
【3.未払い残業代請求により倒産する企業が増える】
未払い残業代総額が増えたことで、未払い残業代問題をきっかけとして倒産する企業が増えることになりそうです。
これはありうる話で、2年でさえ数百万円になることはザラにあるので、5年になるとすごい金額になりそうです。
【4.企業が雇用に対して消極的になる】
労働生産性の低い業種では雇用を敬遠する流れが加速する可能性があります。現にチェーン飲食店ではタブレット端末を使って注文を無人化し、少人数で店舗を回せるように変えています。配送・輸送の分野でも無人化、自動化を進める方向に向いていくことでしょう。
なかなかAIといい、人手がいらない方向になっていきますね。。
終身雇用を維持できなくなってきているとトヨタの社長も言っていましたが、時代は変わってきましたね。対応をしっかりとっていきましょう!
- 2019-08-15
- comments(0)
- by 豊田シティ法律事務所